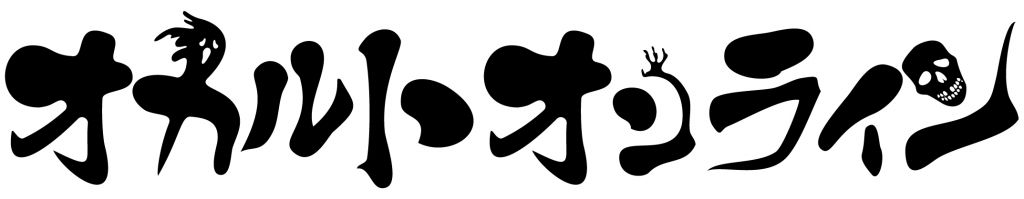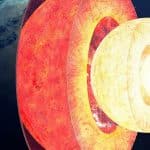オルレアンを解放したジャンヌ・ダルクは、当初からの声の指示であった「シャルル7世のランスでの戴冠式」を目指します。
オルレアン解放戦で敗北したイングランド軍はロワール川を中心とした各拠点に逃げ込んでいました。解放の勢いは止まらずにフランス軍はこれらの残党を次々と攻め落とし、イングランド軍を追い込んでいきます。
そして、追撃戦の中でも最も戦果があったとされるパテーの戦いが始まります。
このパテーの戦いでは、ジル・ドレは「救国の英雄」と呼ばれる大戦果を挙げ、ジャンヌ・ダルクの戦友と呼ばれた人物の多くも活躍しました。
オルレアンの解放から約1ヶ月ほどの時間を経て、ロワール川周辺の勝敗は完全にフランス軍が勝利を納め、いよいよランスでの戴冠式に向けた作戦が練られることになりました。
しかし、ランスまでの道のりには敵対関係であったブルゴーニュ公の領地を通らなければならず、行軍には困難が予想されていたのです。
ジャンヌ・ダルクの戦友と呼ばれた人物

画像引用元:パテーの戦い
ジャンヌ・ダルクには戦友として知られている人物が数名いますが、これらの多くはジャンヌ・ダルクが参戦した短い期間の戦い、オルレアン解放戦からイングランド軍への掃討戦となったパテーの戦いと後のパリ包囲戦において一緒に行動を共にした人物のことを指します。
代表的な人物は以下の通りです。
ラ・イル(軍人)
1428年10月頃からオルレアンの防衛をしていたフランスの将軍で、ニシンの戦いなどで敗北をするもジャンヌ・ダルクが援軍に参戦したあとは1番の忠実な部下と言われるほどジャンヌ・ダルクに従ったとされる。
ジャン・ポトン・ド・ザントライユ(軍の指揮官)
1421年頃からシャルル7世の陣営で戦ったフランス軍の指揮官であり、ラ・イルと同郷の人物。数々の戦争で活躍しジャンヌ・ダルクとも戦友になる。
ジャンヌ・ダルクの奪還を試みた戦争でも活躍し、晩年までシャルル7世に尽くしたことから後にラ・イルと並んでフランスでもっとも勇敢な指揮官と評された。
ジャン・ド・デュノワ(貴族・軍人)
シャルル7世の従兄弟にあたる人物で1415年の時点でイングランド軍と戦っていた。何度かイングランド軍の捕虜になるも、難を逃れオルレアン解放戦では総司令官を務めていた。ジャンヌ・ダルクが捕まる最期まで側で戦っていたとされる。
ジル・ドレ(男爵・フランス元帥)
オルレアン解放戦以降、もっともジャンヌ・ダルクに陶酔していたと言われる人物。ランスでの戴冠式でフランス元帥に認められ、さらに「救国の英雄」とまで呼ばれた。
パリ包囲戦までジャンヌと行動を共にする。しかし、ジャンヌ・ダルクが捕まった後は狂気じみた行為に走り悪名を残すことになる。
ジャン2世(アランソン公)
シノンですでにジャンヌ・ダルクとの面識があったが、1424年から29年までの5年間をイングランドの捕虜として過ごしていたため、身代金の問題でオルレアン解放戦には不参加だった。その後、金銭問題を解決した後にジャンヌ・ダルク達と追撃戦になったパテーの戦いなどで活躍。王太子派の中では最もジャンヌ・ダルクを支持していたと言われている。
アンドレ・ド・ラヴァル(貴族・軍人・フランス元帥)
ジル・ドレの親戚にあたる人物で、オルレアン包囲戦からその後のランスの戴冠式までジャンヌ・ダルクと行動をともにした1人。ジャンヌ・ダルクが処刑された後もシャルル7世の忠実な臣下であり続け1456年に王太子ルイが反乱した際もシャルル7世側で戦っている。百年戦争を終結させた人物の1人でもある。
ジャンヌ・ダルクが評価された経緯
ジャンヌ・ダルクがオルレアン行きを許可された事で、オルレアンには王太子側やアルマニャック派の有力な人物が援軍として駆けつけましたが、ジャンヌ以外の人物は当時のフランスにおける司令官や貴族がほとんどであり、元々の地位があった人物ばかりでした。
一方でジャンヌ・ダルクは予言や数々の行動によって認められた人物ではありましたが、生まれのバックボーンという物を持たなかった為、ジャンヌ・ダルクという存在自体を疎んじた人々も存在したのです。
例えば、シャルル7世の一番の部下であったラ・トレモイユは、ジル・ドレに対してジャンヌ・ダルクを監視するように指示していましたが、ジル・ドレ自身は間近でジャンヌ・ダルクの戦いを見て陶酔していきます。
他にも、当初はジャンヌ・ダルクの実力や存在に意味を見出していなかった司令官や指揮官などの多くも、オルレアン解放を目の当たりにしていく内に、ジャンヌの見方が変わっていったとされています。
こうして多くの有力な人物にも支持されたジャンヌは王太子シャルルのランスでの戴冠式を行うために北上します。
王太子シャルルの戴冠式

画像引用元:シャルル7世(フランス王)
ジャンヌ・ダルクが「声」として聞いていた「オルレアンの解放」、そしてもう1つの重要な儀式が王太子シャルルの「ランスでの戴冠式」でした。
アルマニャック派である王太子シャルルを、ランスで正式に王として成立させることには、当時のフランスの伝統的な意味合いも持っており、正統な王の証を立てる重要なものだったのです。
ランスまでの移動は当初の予測ほど困難もなく、ジアン城からランスまではイングランド軍やブルゴーニュ公の軍勢にほとんど干渉されることもなかったそうです。
大きな理由としては、パテーの戦いなどで疲弊していたイングランド軍は本国に援軍要請をしたものの、距離的な問題が発生しランスへの北上を阻止できなかったことが指摘されています。
また、ブルゴーニュ公に関しては王太子シャルル陣営と和解の歩を進めていたとも言われています。いずれにしても大きな弊害は起きずにランスの大聖堂で7月17日に戴冠式が行われます。
これまではあくまでも王太子であったシャルル7世はこの戴冠式をもって正式なフランス国王に就任します。
しかし、ジャンヌ・ダルクにはまだ課題が残っていたのです。それは「声」の指示する「フランスを救え」という言葉でした。
ジャンヌ・ダルクが捕まった対ブルゴーニュ公軍戦

画像引用元:ジャンヌ・ダルク
ランスでの戴冠式が終わったシャルル7世とジャンヌ・ダルク。
ここから少しずつ2人の意見が食い違ってきます。ジャンヌ・ダルクは戴冠式が終わってフランス北部の都市を訪れていたシャルル7世に対してパリへの攻撃を提言しましたが、シャルル7世はブルゴーニュ公との正式な和解を優先させることを望みます。
ブルゴーニュ派とアルマニャック派であったシャルル7世との間には深い亀裂が走っており、交渉は難航が予想されていました。この交渉においては、一旦は和平交渉に入ろうとしたもののブルゴーニュ公フィリップ3世は和平交渉を反故にし、パリの守備のためにイングランド側へ兵を派遣したと言われています。
これによってフランス側はパリへの進軍を決定し、7月17日の戴冠式から僅か約2ヶ月後の9月8日にパリ包囲戦が始まります。
こういった背景もあり、ジャンヌ・ダルクは戦友であったアランソン公などと軍を編成し、パリ目前のサン・ド二まで進軍をしますが、パリはブルゴーニュ公の援軍とイングランド軍によって強固な防衛体制が構築されており、総攻撃を仕掛けることは出来ませんでした。シャルル7世は軍隊への一時退却を指示し、パリの攻略には失敗に終わります。
その後、ジャンヌは中央フランスで軍事行動を進めていましたが、これら一連の行動は民衆の声を中心としたものであり、フランス軍の軍人的な行動に変化していったといいます。
当初のジャンヌ・ダルクは「神の声」を目的として行動していましたが、次第にジャンヌ行動は民衆の声に左右されるようになったとも言われています。
軍人ジャンヌ・ダルクの捕縛
9月8日のパリ包囲戦では、最後の最後まで戦場で指揮を取っていたジャンヌ・ダルクでしたが、戦闘中に負傷し、翌日の9月9日にはラ・トレモイユ(シャルル7世の部下であり、ジル・ドレにジャンヌ・ダルクの監視役を命じた人物)の意向を組んだシャルル7世の撤退命令を受けて戦線を離脱、10月のムイエ包囲戦にて軍に復帰します。その後11月、12月とロワール包囲戦に参戦するも、これも失敗に終わります。
12月29日にはジャンヌ・ダルクとその家族は貴族の身分に引き上げられますが、フランスとイギリスの間には休戦協定が結ばれ、ジャンヌは数ヶ月に及び”何も出来ない期間”を無為に過ごしてしまいます。
1430年3月23日にジャンヌは当時の異端とされていたカトリックのフス派へと書簡をあてています。
「あなたたちの妄執と馬鹿げた妄信はお止めなさい。異端を捨てるか生命を捨てるかのどちらかです」
引用元:ジャンヌ・ダルク
ブルゴーニュ公の軍は、休戦期間が終わる直前にコンピエーニュというシャルル7世を支持していた都市の包囲に取り掛かります。当然コンピエーニュからは救援要請が求められ、これに真っ先に応じたのがジャンヌ・ダルクの軍でした。しかし、この当時のジャンヌ・ダルクの軍には副官ジャン・ドーロンに加えて、フランス正規軍ではない約200名の兵士という少人数でした。
コンピエーニュに入城したジャンヌ・ダルクの軍は、ブルゴーニュ公軍の砦に向かって突撃するも敗走し、ジャンヌは自らを殿として戦い抜きました。
この時、ブルゴーニュ公軍の軍勢は6000人以上であったと言われており、戦況は絶望的でした。
先に自分についてきた兵士をコンピエーニュへ避難させて、市門前で奮闘していたジャンヌ・ダルクはついに馬から引きずり降ろされて、捕らわれの身になってしまいます。
常に神に対して献身的であったフランスの英雄ジャンヌ・ダルクは民衆の盾となり、1430年5月23日、ブルゴーニュ公によって身柄を拘束されます。
ジャンヌ・ダルクの最期と渦巻いた陰謀

画像引用元:ジャンヌ・ダルク
捕虜の身になったジャンヌ・ダルクには数多の陰謀と試練が待ち受けていました。
囚われたジャンヌ・ダルクは当時のパリ大学神学部から異端として目をつけられており、ブルゴーニュ公へ引き渡し要求の書簡を送っており、ジャンヌ・ダルクへの異端審問を狙っていました。
また、同時期にジャンヌ・ダルク確保にイングランド側のベドフォード公なども政治的な介入を狙って、配下の聖職者であるピエール・コションという人物を用いて、ジャンヌをイングランド王に引き渡す工作をしています。このピエール・コションという人物が事実上、ジャンヌ・ダルクの運命を決めたとも言われています。
ジャンヌ・ダルクをイングランド王に引き渡す役目を担ったピエール・コション
ピエール・コションという人物は元々ブルゴーニュ派であり、さらにパリ大学やイングランドとも深い関係にあった人物でした。
ブルゴーニュ公の目論みはジャンヌ・ダルクを異端と認定させることで、シャルル7世の王位の正統性を乏しめることが狙いであったため、配下であったコションはイングランド王やパリ大学の間を繋ぐ役割を務め、あらゆる手段を用いてジャンヌ・ダルクをイングランドに引き渡すことに貢献したのです。
さらに、ジャンヌ・ダルクの異端審問においても審問官として参加し、ジャンヌ・ダルクを貶めたと言われています。
シャルル7世がジャンヌ・ダルクを助けなかった?
ジャンヌ・ダルクが捕虜の身になった時に、実質的にジャンヌの功績によってフランス王になったシャルル7世は救出に動かなかったという説があり、シャルル7世のジャンヌ・ダルク引き渡し介入に対して批判的な研究者や歴史家は数多くいますが、最近の研究では、シャルル7世や多くの貴族は少なくとも引き渡しに関しては動いていた形跡もあったそうです。
ジャンヌ・ダルク自身はブーヴルイユ城に幽閉されていたと言われており、自力でも何度か脱出を試みています。
何度か移送された後に、ブルゴーニュ公領であるアラスに監禁されていた時にはヴェルマンドワの塔から21メートル下まで飛び降りたという逸話も残っており、ジル・ドレなどはルーアンを攻撃してジャンヌ・ダルク奪還戦を行なっていました。
しかし、諸侯の努力は叶わず、異端審問が行われたルアンへと身柄を移送されます。
ジャンヌ・ダルクに対する異端審問
ジャンヌ・ダルクに対するイングランドやブルゴーニュ派勢力の異端審問はほぼ出来レースであり、その裏にはイングランド王でありながらフランス王にもなったヘンリ6世やピエール・コションなどによって主導的に進められたとされています。
簡潔に言えば異例の手続きによって異端審問までの流れは作られたものであったという事です。
※具体的には裁判を維持するための物的証拠確保や当時の法的根拠がないまま異端審問が開始されたとされています※
ジャンヌ・ダルクが捕虜の身となった1430年5月23日から約半年後、1431年2月21日からおよそ3ヶ月間にわたって異端審問が行われました。
当時、異端審問は教会が主体で行うものであったため、教会の裁判にかけられる人物は教会の保護と監視の下に置かれていましたが、ジャンヌ・ダルクはブーヴルイユ城内の牢獄で過ごしています。
異端審問では、様々な尋問に対してジャンヌ・ダルク1人が答えを出さなければいけないものでしたが、決定的な審判となったのはジャンヌが獄中で男性の服を着ていたことでした。
※当初はジャンヌ・ダルクが聞いた「声」について焦点が当てられてましたが、最終的には服装の問題で追い詰められます※
ジャンヌは最初の判決が下った1431年5月24日の判決中に一度だけ悔悛の誓い(自らの過ちを認めてカトリック教会に戻る表明)を話し、書状にも署名をして罪を赦されます。
しかし、それから4日後の5月28日には悔悛の誓いで義務付けられていた女性用の服を再び男性用の服に戻してしまいます。
判事には自分の意思によって男性の服が好きで着たと答え、さらに4日前の悔悛の誓いは、火刑に処される恐怖心から出た偽りであったことも語りました。
当時の異端審問では回心した人間が再び異端に戻ると救われる道はなく、1431年5月30日、オルレアンの乙女としてフランスを救ったジャンヌ・ダルクはヴェー・マルシェ広場において火刑になり、その生涯を終えるのです。
回心したジャンヌが再び異端となった謎

画像引用元:ジャンヌ・ダルクの列聖
5月24日の回心によって決められた誓いを守っていれば、ジャンヌ・ダルクは教会に戻ることを許され、命を落とすこともありませんでした。
しかし、実際には5月28日には自らの本来の意思を通して火刑にされてしまいます。
この理由については現在も数多くの議論になっており、ハッキリとした理由は判明していません。
しかし、近年の研究では回心した後、再び牢獄に入れられていたジャンヌは女性用の服を盗まれ、男性用の服しか着れない状態にされていた事や、牢番やイギリス人による性的暴行の危険があったことを訴えていたという証言などもあります。
さらにジャンヌ・ダルクの異端審問での態度に関しては言えば、当時の宗教観や情勢から見れば異端判定は当然になることも指摘されています。
ローマ・カトリック教会においての異端者は悪魔との契約者であり、排除すべき存在とされていましたが、それに加えて異端審問を行う聖職者は教皇代理と同じ権限を持つ相手でもあったのです。そして、当時のローマ・カトリック教会はキリスト教における絶対的な権力の中心でもありました。
また、この状況を理解していた聖職者達の一部はジャンヌ・ダルクに対して何度も”現実的に助かる方法”としての回心や忠誠を望んでいたという形跡もあります。
真相はやはり不明ですが、後に復権裁判では、ジャンヌ・ダルクは殉教者であったことが認められ、コーションが無実の女性に罪を被せたという判決によって1456年7月7日にジャンヌに無罪とする判決が出ています。
そして、死後数百年が経った1920年5月15日に、ローマ教皇ベネディクトゥス15世によって列聖され、現在ではカトリックの聖人として扱われることになります。
さいごに
復権裁判での判断や、列聖に関して別として、真実のジャンヌ・ダルクは神の声を聞いた少女だったのではないでしょうか?
火刑に処されることを分かっていながら自らの意思によって聞いた声と幻視を信じた上で信仰を曲げなかったことはもちろん、現実的にオルレアン解放と王太子シャルルの戴冠式を実現したのは他でもないジャンヌ・ダルクの功績でした。
たった19歳でその生涯を閉じたジャンヌ・ダルクでしたが、ジャンヌの功績は今後も多くの人々によって讃えられるでしょう。
参考図書
[amazonjs asin=”4487761530″ locale=”JP” title=”ジャンヌ・ダルク”] [amazonjs asin=”4309762417″ locale=”JP” title=”図説 ジャンヌ・ダルク (ふくろうの本)”]