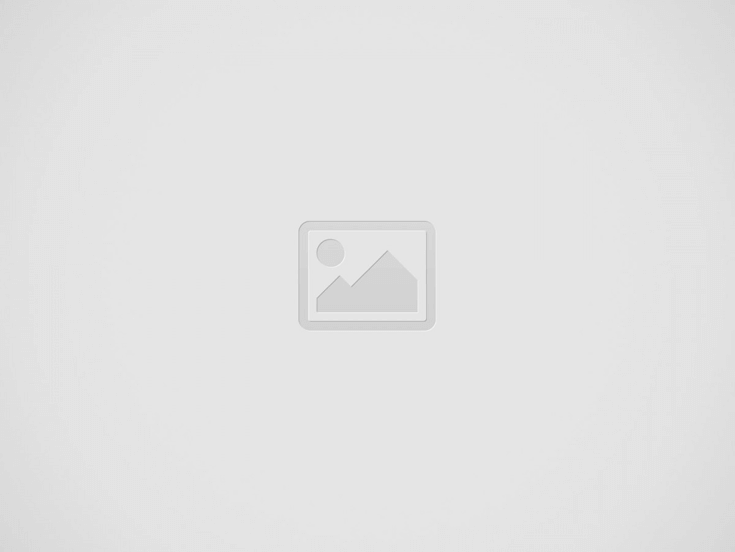

私たちは普段、いろいろなものを見て、聞いて、触れて生きています。
昨日食べたカレーの味や聞いた音楽、観たドラマも覚えていますよね。
しかし、そのどれもが「実際に存在している」といえるでしょうか?
「全て自分の脳内で起こっていることで、触ったり見たりしたと脳が錯覚しているだけ」
こう考えたことはありませんか?
今回はそんな思考実験「水槽の脳」と仮想現実の世界について紹介します。
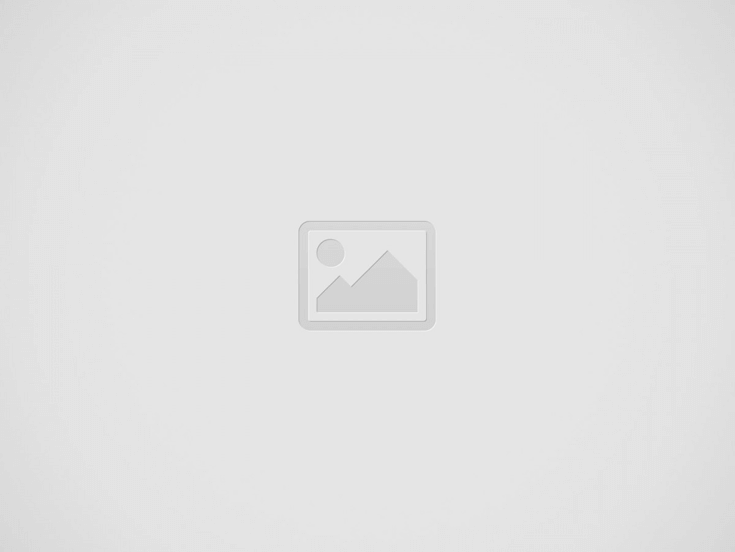
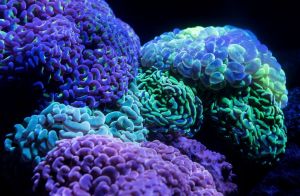
「水槽の脳」とは、1982年に哲学者のヒラリー・パトナムによって提唱された有名な思考実験です。
あなたは手も足もあり、他の人や動物と何ら変わりなく普通に過ごしていると思っています。
しかし実際のあなたは、脳だけが水槽の培養液の中で多数の電極がつけられている状態です。脳以外の器官はあなたには存在しません。
朝起きて太陽の光を眩しく感じたのも、ご飯を美味しいと感じたのも全て脳に与えられた電気信号による錯覚なのです。
似たような世界観はSFの世界でもよく使われており、映画「トゥルーマン・ショー」や「マトリックス」が有名です。
現実世界に生きていると考えていても、実際は第三者によって単なる情報を与えられ続けているだけ、という思考実験です。
かなり突拍子もない話に聞こえますが、「水槽の脳」の仮説を誰も否定できません。
古くからこういった現実世界に対する懐疑的な考えはあります。
例えばプラトンは「洞窟の中で座らされている人は、壁に映し出される影を実体だと思い込んでいる。同様に我々も現実世界という影を実体だと思い込んでいる」といいました。
デカルトは「われわれは夢を見ているか、悪魔に騙されているのかもしれない」と現実世界を疑いました。
「水槽の脳」はそれらと比べれば、現実的に想像できる範囲の話なのでより説得力があるのです。
近年では、仮想現実の技術が発達し、水槽の脳の世界観は実現しつつあります。
近年、VR(仮想現実)と呼ばれる技術が進歩しています。
VRゴーグルをつけてゲームをすると、もうほとんどゲームの世界に入ったような感覚になり、よりゲームを楽しめるのです。
ゲームの場合、VRを体感できるのはゴーグルをつけているときのみで、視覚的体感がほとんどです。
極端にいえば、この体験を脳のあらゆる感覚で四六時中続けられる技術が開発された場合、もうVRの世界から出てこなくてもよくなる日が来るのではないでしょうか。
VR(仮想現実)は一見素晴らしい技術に感じますが、使い方を間違えるととても危険であるといいます。
VRには、大きく分けて以下の4つのリスクがあります。
このリスクを説明していきましょう。
「モデリング理論」からうまれた「社会的学習」という理論をご存知でしょうか。
「社会的学習」とは、「一定の条件が満たされていれば人は他人の行動を模倣して身につける」というものです。
比較的数は少ないものの、VRの暴力的なシーンを含むゲームが存在します。
VRは従来のゲームよりも世界観に没入してしまいます。
VRによって暴力を行ってしまうと、暴力行為を社会的学習として学習してしまう可能性が高いのです。
VRは普通のゲームよりもいっそうゲームにのめりこんでしまいます。
現実により近いため、「VRの世界だけで生きていく」という考えに抵抗なくはまってしまうのです。
VRでは自分の好きなように世界をデザインできるため、その世界にこもったまま現実の世界に出てこない人が続出する未来は簡単に予想できます。
VRを長時間の使用をする場合は、細かく休憩しながら使うことが推奨されています。
VRは五感を酷使し、かなりの疲労感を伴うのです。
ある海外のYouTuberが「VRの世界で25時間過ごしてみた」という動画を投稿しました。
その人いわく、「全ての物事が上っ面だけ、非現実的なもののよう」に感じるそうです。
今現実に見ているものが現実のものなのか、VRのものなのか、区別がつかなくなってしまうのです。
現実の世界を生きるには、当然食べ物や飲み物といった資源を必要とします。
しかし、私たちの脳が人工的なものとなり、肉体を必要としなくなるとどうでしょう。
脳に電気信号さえ送ることができれば、そもそも仮想現実から出てきてご飯を食べる必要もなくなります。
より豊かで自由な仮想現実の世界を求めて、肉体を捨ててVRの世界へ移住する人が出てくるのもそう遠くない未来かもしれません。