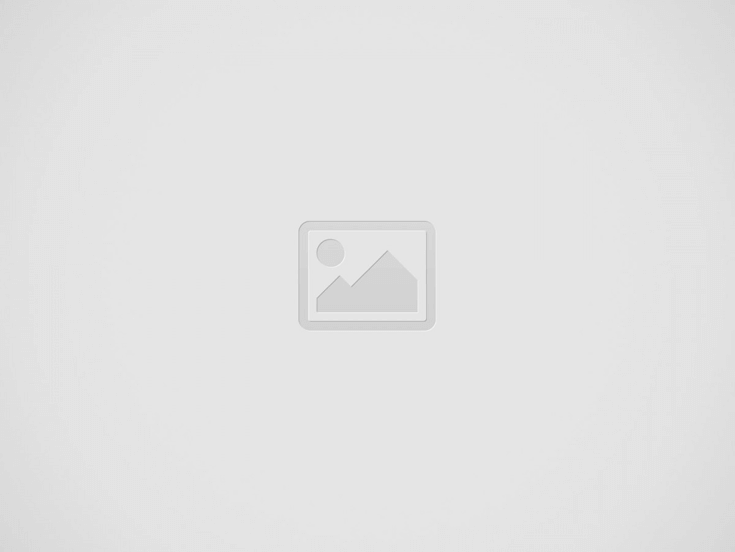

ルネサンス期のイタリアで活躍し、「万能の人」と称される偉人、レオナルド・ダ・ヴィンチ。
彼の生い立ちや作品から、「レオナルド・ダ・ヴィンチとはどんな人物だったのか?」を紐解いていく連載も、今回で第4回になります。
レオナルドの出生から詳しく知りたい方は、過去の連載をぜひご覧ください。
今回は、レオナルドが画家として独立した後、最初に1人で描いたとされる作品『ブノアの聖母』の紹介・解説と、
などについてまとめています。
師匠であるアンドレア・デル・ヴェロッキオと共同で制作した(諸説あり)『受胎告知』で画家デビューを果たした、レオナルド・ダ・ヴィンチ。
その後、彼個人に対しても、徐々に仕事が舞い込み始めます。
この頃に依頼されるテーマはほとんどが「聖母子像」で、様々な画家が、依頼主の意向に沿う聖母子像を描いてきました。
聖母子像とは、聖母マリアと幼子イエス・キリストを一緒に描いた宗教画のこと。
ご多分に漏れず「聖母子像を描いてくれ」と依頼されたレオナルドが描いた作品が、今回ご紹介する『ブノアの聖母』です。
一見すると、聖母マリアと幼児のイエス・キリストが戯れる様子が描かれている、典型的な聖母子像です。
『ブノアの聖母』は公開当時から人気を博していましたが、一方で「斬新すぎて修正された」とも言われている、レオナルドの異次元的な表現を楽しむことができる作品でもあります。
さて、この『ブノアの聖母』のどこが斬新すぎたのか…?
その詳細を見ていきましょう。
『ブノアの聖母』が斬新すぎた最大の理由は、聖母子が聖母子らしくないというところ。
このことについて、これ以前にレオナルドが描いた『カーネーションを持つ聖母』と見比べてみましょう。
『カーネーションを持つ聖母』
『カーネーションを持つ聖母』からは、
といった印象を受けます。
しかし、当時の聖母子像は、このように無機質なものが正道とされ、どこか神聖さを感じさせるものが主流でした。
しかし、この次にレオナルドが描いた『ブノアの聖母』を、もう一度見てみましょう。
そのすべてに人間らしい温かみが感じられたり、生き生きとした印象を受けませんか?
我が子を慈しみ、愛情を持ってあやしているマリアは、神聖さとは程遠く、親近感すら感じさせます。
この親近感が、当時の聖母子像のイメージとあまりにもかけ離れていたのです。
もし、この光輪がなかったら、ひと目見て「これが聖母子像だ」と判断することは難しいでしょう…。
先ほど「光輪がなければ聖母子像と判断できない」と説明しましたが、実は『ブノアの聖母』には、明確に聖母子像と判断できる仕掛けが施されています。
ユーモアのセンスに長け、自身の作品に様々なトリックやなぞなぞを残すレオナルドならではの仕掛けに、あなたは気づくでしょうか…?
その仕掛けとは、マリアとイエスが手に持つ「白い花」にあります。
この白い花をよく見てみると、イエス・キリストを象徴する「十字架」の形をしていることが分かります。
また当時は、
「人間の目からは、最も重要なものを視野の中心にとらえる光が発せられている」
と考えられていました。
この考え方を応用したレオナルドは、マリアが最も大切に思う我が子を見つめさせ、イエスを自身を象徴する白い花(十字架)に夢中にさせています。
このことが、『ブノアの聖母』が紛れもなく聖母子像であることを示しているのです。
レオナルドは、2人の神聖さを徹底的に排除しているにも関わらず、「これは聖母子像である」と明確に表現することに成功しているのです。
「レオナルド・ダ・ヴィンチの幼少期【連載No.1】」でもご紹介した通り、レオナルドは幼い頃に母親と離別しています。
彼は祖父母や親戚に大切に育てられましたが、この別れの経験は、彼の生涯にわたって「理想の母親像」を想像させることとなりました。
有名どころでは、『モナ・リザ』にレオナルドの理想の母親像が描かれているとされていますが、『ブノアの聖母』もまた、
などが描かれているように感じられます。
画家としての技量や一瞬の表情を捉える観察力はもちろん、レオナルドの母親に対する想いが込められているからこそ、この聖母マリアの慈愛に満ちた表情が描けたのではないでしょうか。
レオナルド・ダ・ヴィンチの内面が顕著に現れているという意味では、『ブノアの聖母』は彼の代表作と言えるでしょう。
画家デビュー直後から斬新な絵画を描いてきたレオナルド・ダ・ヴィンチですが、彼は絵画以外にもあらゆる物事に興味を持ち、あえて悪く表現するなら「飽き性」でもありました。
そんなレオナルドには、『モナ・リザ』のような未完の作品も数多く残されており、それは画家デビュー直後も例外ではありません。
次回は、未完に終わったからこそ彼の凄さが分かる『荒野の聖ヒエロニムス』をご紹介します!